各部門・センター
不整脈センター
各部門・センター紹介
ごあいさつ
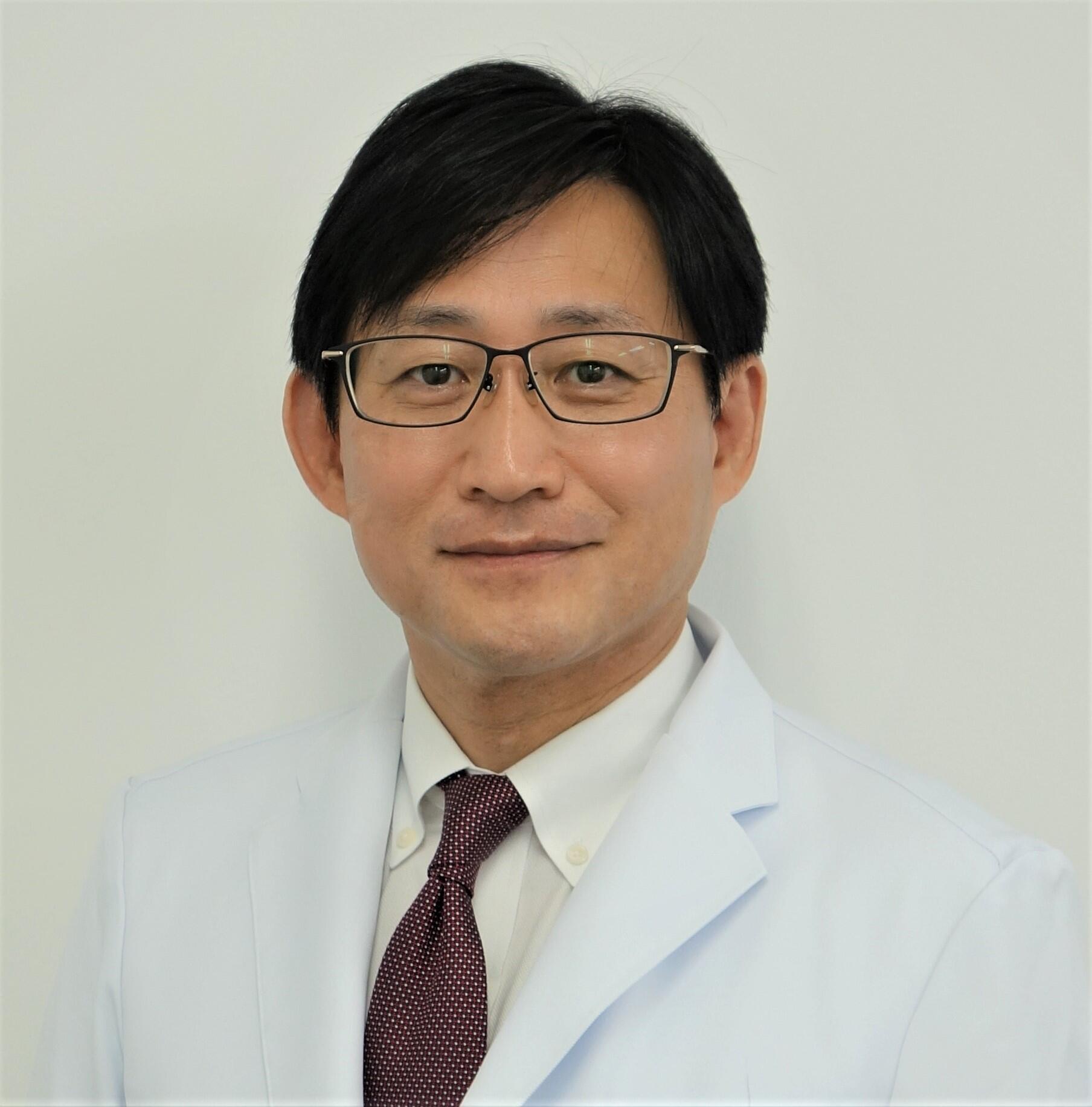
福岡大学病院の不整脈診療は、病院開設以来、数多くの不整脈疾患の症例を診療し地域医療に貢献、また新しい知見を発信してまいりました。現在、高齢化に伴い不整脈疾患は増加の一途で、関わる診療の需要や必要性はますます増加しています。特に不整脈非薬物治療において、最先端の3次元マッピングシステムを用いたカテーテルアブレーション、また最新の心臓植込みデバイスを駆使したペースメーカ、植込み型除細動器、心臓再同期治療を実施しています。当センターでは日々進化し続ける最先端医療やテクノロジーに対応するため、医療者は医師のみならず看護師、放射線技師、臨床検査技師や臨床工学技士など多職種にわたり、診療科・部門は循環器内科のみならず心臓血管外科、救命救急センターや臨床検査・輸血部などで、こうした横断的協力と包括的運営によるチーム医療で最善最適の診療を提供しています。
不整脈とは何か
不整脈はほとんどすべての方に診られる疾患で、概して、心臓の電気活動が正常範囲を超え、異常に多すぎたり少なすぎたり、不規則になったりする状態を指します。また、心臓の形態や機能に異常がなくても不整脈が発生することはしばしばあり、元の心臓に異常があればなおさら多く発生します。自覚症状として、動悸、脈の結滞、息切れ、胸痛、失神、突然死などがありますが、看過できるものから命にかかわるものまで重症度は様々です。たとえ不整脈があっても自覚症状がなく経過し、健診での心電図検査、または他の心身の不調で病院を受診して初めて不整脈の存在に気付かされる場合があります。したがって、日常生活において自己検脈や健診での異常の検出、また日常診療では身体診察や心電図検査でできるだけ不整脈を検出ないしは予知し、適確に評価し適切に対応する必要があります。
特徴・特色
診断は心電図検査により判明します。
治療は非薬物治療と薬物療法の2つに大別でき、下記のような特徴があります。
カテーテルアブレーション(非薬物療法)
対象となる疾患は心房細動・粗動、心房頻拍・期外収縮などの心房頻拍性不整脈、また期外収縮や心室頻拍などの心室頻拍性不整脈が対象になります。最先端の3次元マッピングシステムを用いて、不整脈の回路や発生源を同定し、高周波、冷凍凝固やパルスフィールドなどのエネルギー源を駆使して治療します。現在、年間約300例のカテーテルアブレーションを施行しています。
植込み型心臓電気デバイス(非薬物療法)
洞不全症候群や房室ブロックなどの徐脈性不整脈に対するペースメーカ、多形性心室頻拍や心室細動などの致死性不整脈に対する植込み型除細動器(ICD)や電気的非同期により心不全が発生ないしは増悪するものに対して心臓再同期(両心室ペーシング)治療などを施行し、現在、年間約200例の植込み型心臓電気デバイス手術を行っています。直近ではリードレスペースメーカ、刺激伝導系ペーシング、リードやデバイス本体すべてを皮下に移植するICDなどの先端医療も取り扱っています。また、原因不明の失神や脳梗塞の症例の原因を明らかにするために植込み型心電計を適応することがあります。心肺停止症例の急性期診療を救命救急センターと協力して行い、引き続き慢性期の評価と治療を行います。
不整脈外科治療・心臓血管外科的アプローチ(非薬物療法)
特に虚血性・非虚血性心疾患に合併する心房細動などの合併不整脈やさまざまな機序による不整脈に対し、その必要性や適応に応じて外科的治療を施します。広範囲の心外膜側アプローチを要する症例やアブレーション治療の合併症などに対しても、心臓血管外科と協力しチームで診療します。
薬物療法
ピルジカイニド、べプリジル、ワソラン、β遮断薬やアミオダロンなどの抗不整脈薬治療のみならず、心房細動の血栓症に対する抗凝固薬、降圧薬やSGLT-2阻害薬など抗心不全薬などを駆使し急性・慢性期の不整脈薬物治療を施します。
